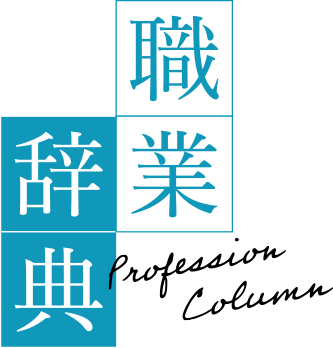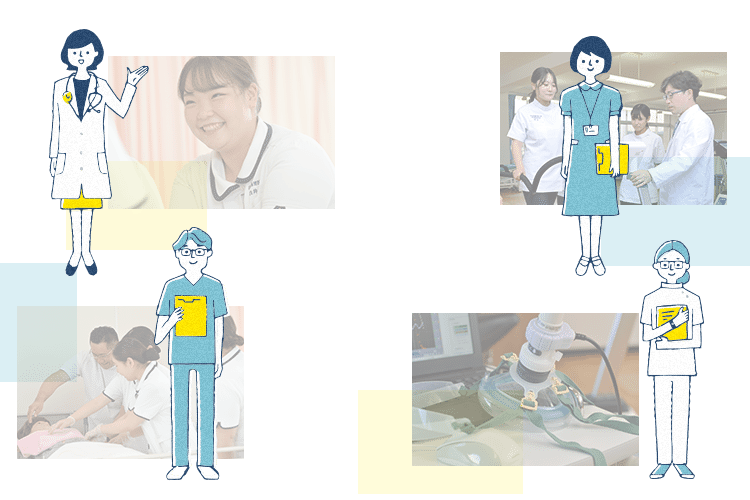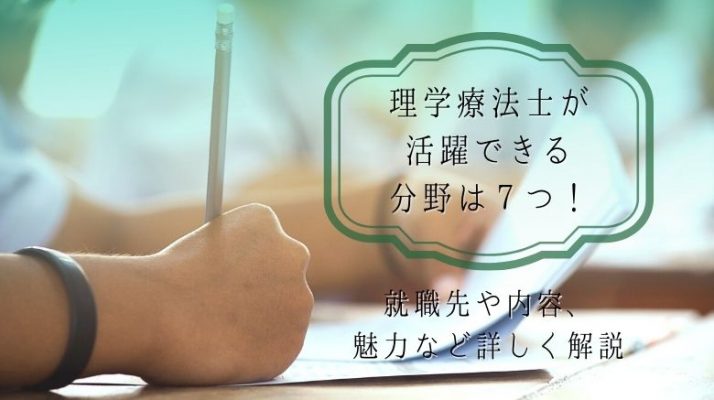理学療法士の適性とは?仕事内容や就職先別の適性なども合わせて紹介
- 理学療法士
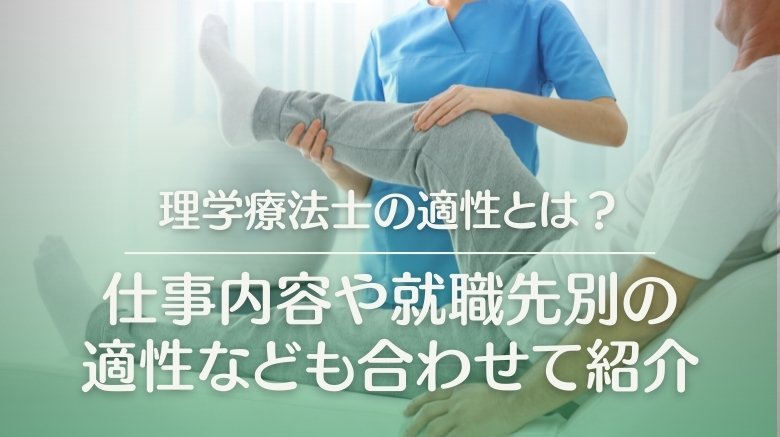
「理学療法士」という職業があります。
その名前だけ聞くと、まず「あの、病気やケガをした人に、リハビリの指導をする人でしょ?」と考えると思います。
確かに間違いではありませんが、理学療法士という仕事を詳しく知ると、その奥深さに驚かされます。
そんな奥深い理学療法士になるには、一体どんな人が向いているのでしょうか?
「身体の動かし方を知って、回復していくメカニズムや訓練方法を学んで、患者さんを指導する」という知識以外に必要な、理学療法士の適性を、本当はどんな仕事なのかを通して知っていただきたいと思います。
目次
理学療法士とは

まずは理学療法士が具体的にどんな仕事なのかを知っていきましょう。
理学療法士の仕事内容
「理学」とは、自然科学や物理学といった、自然界の真理を突き詰める学問であり「理学療法」とは、病気やケガ・高齢などにより、障がいを抱えたり障がいが予測されたりする患者さんに対して、物理的な手段を用いて回復を促す治療法です。
薬や手術などを用いる治療とは違い、物理的手段を用いた理学療法は以下のような種類と効果があります。
- 関節の可動域を広げる、歩く・座るなどの基本的な動作を維持する、筋力や持久力を増強するなどを目的とした、症状に合わせた体操などを指導する運動療法
- 温水や冷水などで患部に刺激を与えたり、水圧や浮力、流水の抵抗などを利用して水中運動をしたりする水治療法(すいちりょうほう)
- 熱や電磁波などで患部を温め、循環の改善や痛みの軽減・リラックスなどを促す温熱療法
- 筋肉に電気を流し収縮・弛緩を起こし、血行を良くすることで痛みや疲労を緩和する電気療法
- 太陽光にも含まれる紫外線や赤外線・可視線を、治療を目的として素肌に照射し内側から温め、生体リズムを整え、血液透過性を高める光線療法
- 筋肉がほぐれ血行が良くなることで痛みの緩和や機能改善が図られ、心理的にも効果を発揮するマッサージ
理学療法士は、医師の元で行われる治療と足並みを揃え、医師の指示により以上のような治療を行い、患者さんの運動機能の回復や改善をサポートする仕事です。
これからの日本に必要な仕事
日本の高齢化はこれから急速に進み、超高齢社会になると言われています。
このまま高齢化が進むと、雇用・医療・福祉などさまざまな分野が影響を受けると予想され、それは「2025年問題」と呼ばれています。
理学療法士は、超高齢社会による需要が高まっており、養成施設も急速に増えています。
そんな中、病院や診療所で勤務する理学療法士が全体の80%近くを占めているにも関わらず、介護関係での勤務は10%と少なく、現状は人手不足と言われています。
その原因は、介護でリハビリテーションを必要としている高齢者の数が、年々増加の一途を辿っているからなのです。
資格取得者が増えているのにも関わらず、まだまだ必要な分野に理学療法士が行き渡っていない現在と、増え続ける高齢者を抱えていくこれからの日本に、理学療法士は欠かすことのできない重要な仕事と言えます。
理学療法士になるためには

それでは、理学療法士の適性を問う前に、どうすれば理学療法士になれるのか、必要な資格や合格率についてご紹介します。
理学療法士に必要な資格
理学療法士は国家資格ですので、適性も勿論ですが、資格取得が必要です。
国家資格とは、厚生労働大臣から与えられる免許であり、取得するためには、まず国家試験を受けることになりますが、誰でも受けられるわけではありません。
文部科学大臣または厚生労働大臣が指定している養成施設で、決められた期間、専門的に学ぶことで初めて受験資格を得ることができます。
- 4年制大学
- 短期(3年)大学
- 専門学校(3年制・4年制)
- 特別支援学校(視覚障がい者が対象)
高校卒業後、以上のような学校で、3年以上、もしくは作業療法士の資格をすでに持っている場合は2年以上、専門知識を身に付ける必要があります。
理学療法士の合格率
実際のところ、理学療法士の国家試験合格率は80%前後と言われていて、低くはありません。
一般問題160問、実地問題40問の計200問を、2時間40分の制限時間内に解答する国家試験です。
合格のためには養成校に入学し、解剖学や生理学・運動学などを始めとし、リハビリテーションや理学療法など、広範囲に渡る基礎科目を学びます。
そして年次が上がるごとに専門性のある学科と実習が増え、実際の医療機関で指示を受けながら患者さんと接する臨床実習を行うなど、実に様々な知識を様々な形で学び進めていくことになります。
3~4年の養成期間内にそれだけの勉強をこなさなければ受験資格が得られないとなれば、合格率が低くはないと言えど、その努力は簡単なものではないことが分かるでしょう。
理学療法士はどんな人に向いている?

超高齢社会へと加速するこれからの日本において、重要な役割を担うであろう理学療法士になるには、実に沢山の学びが必要になりますが、それでは一体どんな人に向いている職業なのでしょうか?
人と関わるのが好きな人
理学療法は時間をかけて取り組み結果を求める治療であるが故、中には諦めそうになったり挫けそうになったりする患者さんもいらっしゃいます。
そしてリハビリテーションの計画を立てる際や、近年増えている自宅訪問など、ご本人だけでなくご家族と相談して進めていく場面が増えています。
理学療法士には、そんな中で信頼関係を築くためのコミュニケーション能力が必要になります。
人と関わるのが好きな人であれば、治療に対して不安がある患者さんを励まし支え、質の高い理学療法をスムーズに提供することができるでしょう。
観察力・洞察力がある人
理学療法士は専門的な知識をしっかりと身に付けてその仕事に就いていますが、実際に患者さんに接する場合、患者さん自身の関心ごとや表情に気を配り、異変などに気付くことができる、知識以外での視点が必要となります。
広い視野で得た情報を元に計画を組み直したり、よりスムーズにプランを進めたりするきっかけを、日頃から見逃さない観察力や洞察力のある人が、理学療法士には向いています。
心身ともに健康で、人を思いやれる人
身体が不自由で不安定な患者さんに体操などを指導するということは、咄嗟の事態に柔軟に対応でき、時には支えになってくれる指導者でなければならないということです。
そして、なかなか思うように身体機能が回復しない患者さんは、いらだち、時には落ち込み、精神的に不安定になって挫けてしまうことも少なくないでしょう。
そんな時、身体的に力強く支え安心させ、精神的にも共感し励ましながら前向きな言葉をかけ、そのモチベーションを引き出しつつ忍耐強く指導を続ける役目は、心身ともに健康な人でなければ難しいかもしれません。
理学療法士は、患者さんの身体に触れて、言葉を交わしながら回復をサポートする、患者さんにとっては大変近しい存在と言えるので、心も体も健康で思いやりのある人が適しているでしょう。
向上心を持って学べる人
沢山の知識と実習を重ねて国家資格を取得する理学療法士ですが、医学や治療技術の日々の変化に遅れないために、資格取得後も勉強の手は抜けません。
理学療法士になってから最初のうちは、先輩にアドバイスを頂きながら学校で習ったことの確認をしていくことになります。
しかし、患者さんに接する毎日は、患者さんごとで痛むところや症状などが違うことで、接し方を変えなければならず、体験しなければ分からないことの連続です。
患者さんが少しでも早く支障のない日常生活に戻れるよう、最適な方法に繋がる知識や情報を、自分の中で常にアップデートしていくことが必要です。
理学療法士には、ひとつでも有益な知識を身に付け、役立てようという向上心を持って、前向きに学べる人が向いています。
働く場所による理学療法士の適性

理学療法士の働く場所は多岐にわたりますが、そこでも適性を問われる場面があります。
上記の「理学療法士になる適性」に当てはまっていなくても、以下の就業場所に興味があるようであれば、理学療法士の資格を取った後の進路として、考えてみるのもいいでしょう。
医療機関
病院やクリニックなどは、その病気やケガで障がいを負ってからそれほど時間が経過していない患者さんのリハビリが多い傾向となっています。
総合病院などで行えるリハビリ期間の日数には上限があるため、適切なリハビリによる速やかな社会復帰が求められています。
そのような場面での理学療法士には、特に身体機能面に特化した専門知識や技術が多く求められます。
その他にも、がん治療患者さんの体力維持や、高齢の患者さんの機能低下の予防のための指導・訓練も行います。
また整形外科については病院や介護施設などとは異なり、学生さんやスポーツ選手などスポーツリハビリテーションが多く、他にも痛みや動きの悪さを訴える患者さんが多いので、運動器に特化した、結果が早く出せるような理学療法士が求められます。
短い時間で判断してプランを組み立てる能力を育てる場合や、将来スポーツの分野に関わりたい場合は整形外科が向いています。
公共施設
地域の保健センターや、セミナー講師、放課後デイサービスや小児発達支援など、医療機関ではない公共施設での理学療法士の需要もあります。
地域を通して高齢者や子供たちを指導して、相談に乗るなど、身体機能以外の部分でもサポートが必要な方々に指導を行うといった理学療法士は、子供に対するコミュニケーションスキルなど、医療機関とはまた違った適性が必要になります。
病院・介護施設以外
理学療法士の国家資格は、医療や福祉の現場以外にも役立てることが可能です。
スポーツ施設やフィットネス関係、医療書籍の出版社での執筆や、医療機器メーカーでの福祉関連の機器販売、製造業会社の従業員のケア、行政機関の介護福祉課、養成機関の教員なども、理学療法士の資格を役立てて働ける就職先として考えることができます。
まとめ
理学療法士の適性について「理学療法士になるための適性」と「働く場所による理学療法士の適性」の2つの面からご紹介しましたが、いかがでしたか?
患者さんとの距離感から見ると、医師とそれほど変わらないと言えるかもしれないほど、近いところで患者さんを支え、回復をサポートできる理学療法士。
日本保健医療大学では、理学療法士になるために、基本が重要と考えた上で、時代に合った深い知識も身につけられるよう、経験豊かな教員による教育を行っております。
最新の医療技術が学べる教育環境をご用意しておりますので、まずはオープンキャンパスやHPで、学校や学生の雰囲気を見てみてはいかがでしょうか。
理学療法士を目指している方の他、病院や介護施設で働きたいと考えている方も、ぜひお気軽に日本保健医療大学まで、お問合せください。