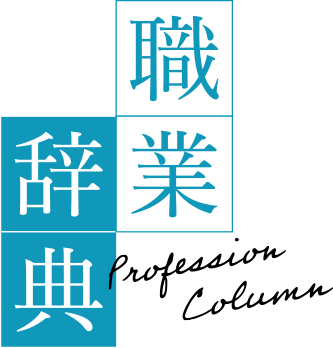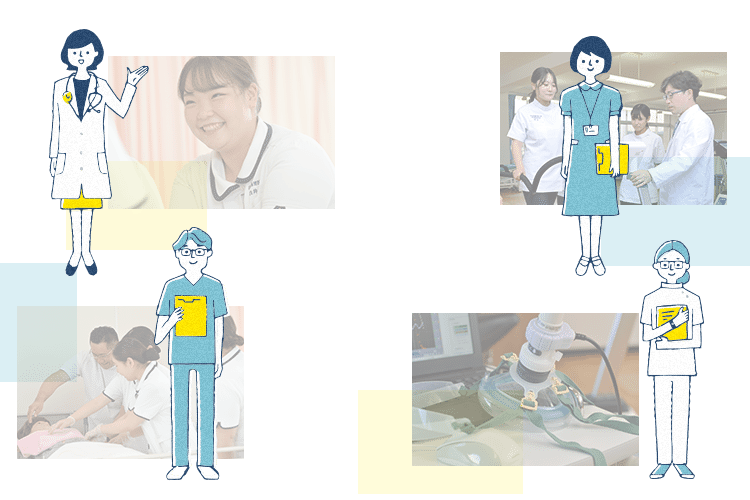看護大学では何を学ぶの?卒業時に取得できる主な資格を紹介
- 看護師
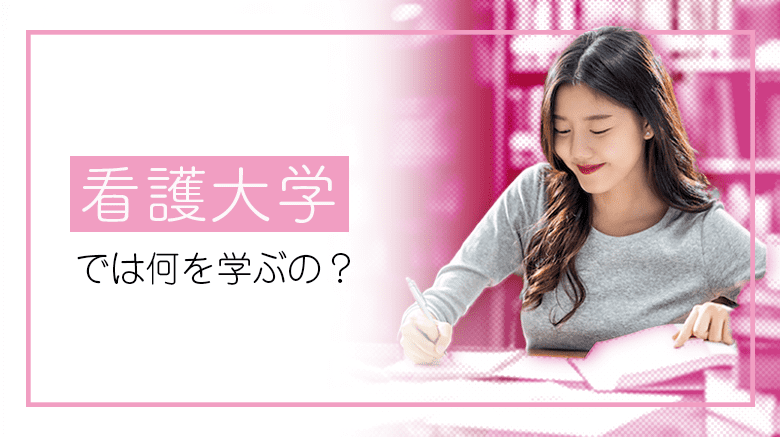
看護師は、医師の診察や指示に基づき、患者さんの診療の補助や入院生活の介助、看護を行う仕事です。具体的には、患者さんの血圧や体温、脈拍などの測定や、医師の指示があった場合の診療器具の受け渡し、患者さんへの注射や採血、点滴、患部の消毒や薬の塗布など、仕事内容は多岐に渡ります。
看護師といえば病院やクリニックで働くイメージがありますが、近年、病院やクリニックだけでなく、介護施設や保育所など活躍の場が広がっています。
また、女性のイメージが強い看護師ですが、男性看護師も年々増加しており、重度の障がいをもっている患者さんのケアや、力強く抵抗される患者さんへの対応など、男性看護師の方が円滑に業務を進められる場合もあるため、今後も活躍の場が増えていくと考えられています。
看護師になるには、国家資格を取得しなければなりませんが、そのためには学校へ通い、学ぶ必要があります。選択肢としては、専門学校、短大、大学の3つがありますが、今回は看護大学では何を学び、どんな資格を取得出来るのかを詳しく解説します。
目次
看護大学で学ぶこととは

看護とは、病気や怪我を負った方の介抱をし、回復するように援助することです。また、病気を予防し、患者さんの家族への心のケアなども含まれています。
看護大学では、このような看護を行うために必要な知識である看護学を学べます。
看護学は大きく分けると、基礎看護学、臨床看護学、看護の統合の3つの分野から成り立っていますが、具体的にはどのようなことを学ぶのでしょうか。
ここでは、3つの看護学について詳しくご紹介します。
基礎看護学

基礎看護学は、看護学の基礎となる理論や技術について学び、研究する学問です。
看護師を目指す者にとって、導入部分となる重要な学問領域で、主に1、2年生で授業を行うことが多く、さまざまな科目に分かれています。
基礎看護学の主な内容
- 看護理論
- 看護過程
- 看護の歴史
- 看護教育
- 看護と他職種との連携
- 看護の役割
- 対象理解の理論と方法
- 看護倫理
- フィジカルアセスメント
- 国際看護
- 治療的看護介入
上記のように知識を深めていく科目だけでなく、実践的な看護技術を習得し、状況に応じて問題解決に対応する能力を養うため、演習を多く取り入れながら学んでいきます。
患者さんが望むような生活をするための援助を考えるために、日常生活の援助技術である食事や排泄、診療に必要な注射や吸引などの高度な看護技術を科学的な視点から学び、自分の中に看護観を芽生えさせていきます。
臨床看護学
臨床看護学は、実際に患者さんに対してどのような処置やケアを行うべきか、実習で体験しながら看護の理論を身につけていく学問です。
臨床看護学の主な内容
- 母性看護学
- 小児看護学
- 成人看護学
- 老年看護学
- 精神看護学
看護実践と、学問としての看護学を繋げるのが、臨床看護学です。各分野の特徴的な疾患や看護を理解していきます。各分野の看護学についての理解を深めるには、形態機能学や臨床病態学などの知識が重要です。
また、学んだ知識を基礎として、演習において実際の臨床場面を想定し、患者さんや家族の抱える問題などに適切に介入し、援助するための方法などを具体的に学んでいきます。
看護の統合
看護の統合では、今までに学んだ基礎看護学、臨床看護学の知識や経験を統合して看護師として実践できるように学んでいきます。
看護の統合の主な内容
- 看護研究
- 看護管理学
- 在宅看護論
- 在宅看護論実習
看護の統合は、実際に保健師や助産師、看護師の看護職として求められる知識や能力を養っていきます。
看護の統合の領域は、新生児から高齢者まで地域で生活する方がいるすべての場所です。現在の日本は高齢化社会となっており、そのような社会情勢や医療情勢の変化にも対応できるよう、患者さんや家族に対するあらゆるケアを科学的に学び、実践を通して責任を持って行動できる能力を身につけていきます。
その他の学習科目
看護大学では、上記のほかにも人体の仕組みや働きを学ぶ解剖生理学、薬学、病理学などの医療分野や、化学、生物学、心理学、哲学なども学びます。大学によっては他学部と合同で学ぶこともあります。
1年生のうちは座学を中心としていますが、2年生になると実際に病院や福祉施設などへ実習に行く機会も増え、実際の現場を通じて看護を学んで行くことになります。
卒業時に取得できる主な資格

看護大学では、卒業時に看護学の学士が授与され、同時に看護師国家試験受験資格を取得できます。看護学を学んだあとは看護師になる方が最も多いのですが、看護師といってもさまざまな種類があります。
たとえば、外来患者を担当する外来看護師や、入院患者を担当する病棟看護師、手術の解除をするオペ看護師などがあり、同じ看護師でも仕事内容が違います。
また、看護大学で取得できるのは、看護師国家試験受験資格だけではありません。ここでは、看護大学卒業時に取得できる資格をご紹介します。
学士の学位
学士とは大学を卒業すると取得できる学位のことです。学士には種類があり、たとえば経済学部を卒業すると学士(経済学)、心理学部を卒業すると学士(心理学)となります。
つまり、看護学士とは看護大学を卒業したということです。看護業界では看護学士のみを大卒として認めるという慣習があります。
看護師国家試験受験資格

看護師になるには、大学または3年以上の教育を受け、看護師国家試験受験資格を取得したのち、看護師国家試験に合格する必要があります。
保健師国家試験受験資格
保健師になるためには、保健師国家試験および、看護師国家試験に合格しなければなりません。卒業と同時に保健師国家試験を受験できるのは、大学の看護学系学部、または、修業年限4年以上の統合カリキュラム採用看護系専門学校で、保健師になるための学科を専攻した者のみです。
上記の方法以外で保健師国家試験受験資格を取得する方法は、看護師養成所または看護大学や短大を卒業後、まずは看護師資格を取得し、保健師養成課程の専攻科のある短大、または保健師養成所にて1年間学ぶ必要があります。
助産師国家試験受験資格
助産師になるためには、保健師と同様に助産師国家試験および、看護師国家試験に合格しなければなりません。助産師の養成課程がある大学では、卒業と同時に助産師国家試験受験資格を取得できます。
助産師の養成課程がある大学以外では、看護師資格取得後に助産師養成学校や、看護短大の専攻科で1年間、看護系大学院で2年間学ぶなどの方法があります。
受胎調節実地指導員
受胎調節実地指導員とは、女性に対して厚生労働大臣が指定する避妊用器具を使用する受胎調節の実地指導を行うものとして助産師、保健師または看護師のいずれかの免許を持ち、都道府県知事の認定する講習を修了した人のことで、通称リプロヘルス・サポーターといいます。
講習修了後、都道府県知事に指定の申請を行うと、免許が交付されます。
養護教諭二種
養護教諭二種は、学校の保健室で児童、生徒の健康管理をする仕事に従事するために必要な資格です。
看護師国家試験および、保健師国家試験に合格し、大学在学中に文部科学省令で定める科目を履修していると、申請により養護教諭二種免許の資格を得ることができます。
あるいは、養護教諭養成過程のある短大、看護専門学校を卒業後、保健師養成所などで保健師資格を取得し、さらに養護教諭養成機関で半年~1年間学ぶ方法もあります。
第一種衛生管理者
衛生管理者は労働者の健康障害や労働災害を防止するために、労働安全衛生法で定められた国家資格で、50人以上の労働者がいる職場では、衛生管理者を選任しなければなりません。
主な仕事は作業環境の管理や労働者の健康管理、労働衛生教育の実施、健康保持増進措置などです。
保健師の免許取得後、労働基準監督署や都道府県労働局へ申請すると第一種衛生管理者資格を取得できます。
保健師以外の方が第一種衛生管理者になりたい場合、受験資格が最終学歴と労働衛生の実務経験年数によって変わります。資格の取得を検討している方は、それぞれの受験資格を満たす必要がありますので注意しましょう。
まとめ
看護大学では何を学び、どんな資格が取得出来るのかを詳しく解説しましたが、参考になりましたでしょうか。
多くの学生は卒業後、看護師の道へ進む方が多いですが、食品製造や医薬品関係、感染症研究、さらには治験の被験者のケアをする治験コーディネーターなど、さまざまな職業に就けます。
人口の21%が65歳以上の高齢者が占める超高齢化社会である日本では、高齢者の割合は今後さらに増え続け、人口の30%程度まで増加するといわれているため、これからの時代はさらに看護師の需要が高まっていくでしょう。
看護大学では、看護師国家資格だけでなく、保健師、助産師の資格が取得できるカリキュラムを設けていることが多く、将来の仕事の選択肢を広げられます。
日本保健医療大学の看護学科では、卒業すると看護師国家試験受験資格だけでなく、保健師国家試験受験資格を得られます。さらに、所定の授業科目を履修し、保健師免許を取得すると、養護教諭二種、第一種衛生管理者の資格も取得できます。
国家試験の出題傾向についての正確な情報提供、経験豊富な教員による学習計画と学習方法のアドバイス、学内の試験結果への適切なアドバイス、国家試験受験から登録までの各種手続きのサポートなど、4つの国家試験対策サポートを行い、学生を徹底的に支援。その結果、看護師国家試験の合格者は全国15位にランクインしています。
生徒一人ひとりに目が行き届くよう、学年担任の複数配置や学習指導教員の配置など、学習面だけでなく学生生活を有意義に過ごすために配慮をしています。
看護を学びたい学生をさまざまな角度からサポートする日本保健医療大学が気になった方は、ぜひ一度お問い合わせください。