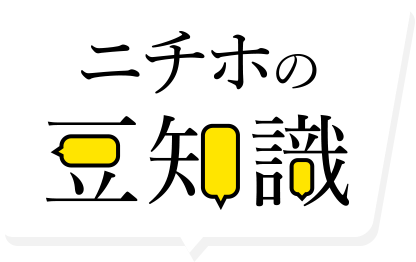大学入学共通テストとは?仕組みや利用するメリットデメリットを紹介
- 入試情報
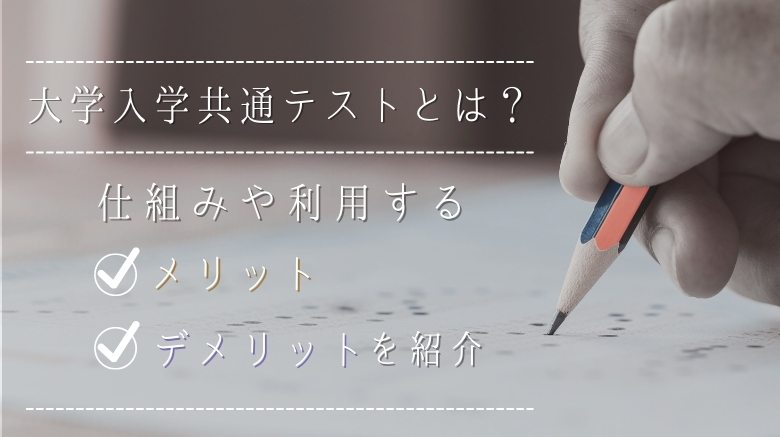
大学入学共通テストとは、大学入学を志願する人の、高校での基礎的な学習の達成度を判定する試験です。これまで行われていたセンター試験に代わって2021年度からはじまりました。
「テレビのニュースなどでセンター試験が実施される様子を見たことはあるけれど、そもそもセンター試験や共通テストってなんなの?」「みんな受けるものなの?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
共通テストは、国公立大学を受験する際の1次試験として、原則受験しなければならない試験です。また、多くの私立大学でもこの共通テストの成績を利用するシステムが設けられているため、大学への進学をお考えの方にとって、共通テストは避けては通れない道だといっても過言ではありません。
共通テストはまだ始まったばかりの新制度であるため、詳しい情報を把握していない方も多くいます。そこで、この記事では大学共通テストの詳細と、利用するメリットとデメリットについてご紹介します。
大学受験をお考えの方やその親御さんは、ぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。
目次
大学入学共通テストとは?
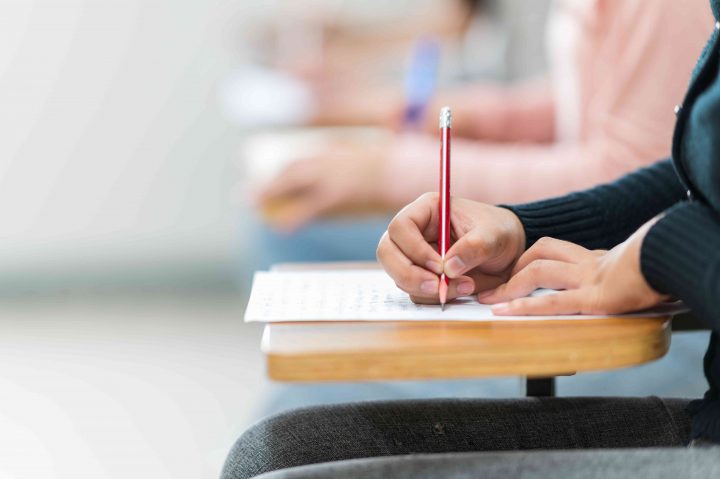
共通テストは、「高校の学習をしっかりと理解できているか」「大学で学ぶにふさわしい学力があるのか」をはかるために行われる大学入試最大のテストです。
試験科目はセンター試験と変わらず6教科30科目が出題されます。しかし、従来のセンター試験よりも、思考力や判断力、表現力を問う問題が増えているという点に注意しなければいけません。
ここではまず、共通テストについての詳しい情報をご紹介します。
なぜ共通テストに変える必要があるのか
そもそも、なぜ従来行われていたセンター試験から共通テストに変える必要があるのでしょうか。
その理由は、国が推し進めている「高大接続改革」にあります。
現在の高校生、小中学生が大人になり社会で活躍する頃には、社会全体に大きな変化が起こっている可能性があります。具体的には、少子高齢化や情報化社会の進展、グローバル化などです。
これらの変化が起こると考えると、これから社会に出る人たちが持っていた方がよい能力は以前とは違ってくるということです。
昔から知識を持っていることは、社会で活躍するために重要ではありました。しかし、AIの発達により、現在では人間が行ってきた仕事を機械が行うことが増えてきています。
情報を蓄積するだけなら人間でなくてもできるようになってきたため、単純な情報処理や記録ではない能力を求められるようになってきたのです。
これからの時代は、自ら問題を発見し、多様な人々と共に解決していく力が必要となります。そのために、「高大接続改革」では、高校と大学、それをつなぐ大学受験をまとめて改革しようとしているのです。
共通テストでは、知識を前提としながらもこれまで以上に思考力や判断力、表現力、そして主体性を持って他者と協力して共に学ぶ態度を見極めます。そのため、従来のセンター試験のよいところは引き継ぎつつも、出題形式や問題の質などが見直されました。
ただ、今のところ2020年1月末に発表されたものが基本方針となっていますが、変更される可能性もあるため注意しましょう。
共通テストの仕組み
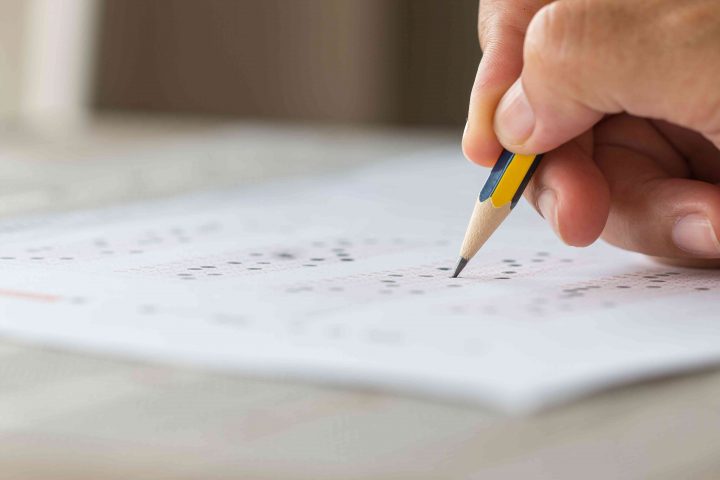
共通テストは、独立行政法人「大学入試センター」と各大学が協力し、全国同一日程、同一問題で行われるテストです。
以下は、共通テストの受験が必要な人です。
- 国公立大学を受験
- 私立大学の共通試験利用
- 私立大学の共通試験併用型
共通テストは国公立大学を受験する際の1次試験として利用され、共通テストと個別試験の合計で合否が決まります。
たとえば、東京大学などでは第1段階選抜という試験が実施されており、大学が設定した基準点を下回ると2次試験を受けられないので注意が必要です。
また、共通テスト利用入試には、「単独型」と「併用型」があります。
単独型は大学入学共通テストの成績のみで合否が決まる方法で、併用型は共通テストのほかに大学独自の試験が課される方法です。科目や配点比率については、大学や学部学科によって違ってきますので、募集要項をよく読むようにしましょう。
とくに注意すべきなのは、理科です。理科は科目選択のパターンが4つあるため、志願する可能性のある大学の受験科目をしっかりとチェックして学習計画を立てる必要があります。
共通テストの出願の流れ
共通テストの出願の流れについても知っておかなければいけません。以下は、共通テスト受験までの流れです。
- 受験案内を入手:9月1日から配布開始
- 成績開示のための手続き:
- 検定料、成績開示手数料を納付:9月1日から10月上旬
- 志願票を作成:9月下旬まで
- 志願票を提出:出願期間は9月下旬から10月上旬
- 確認はがきが送られてくる:10月下旬
- 2次試験募集要項が必要な場合は取り寄せる:11月下旬から12月中旬
- 受験票などが送られてくる:12月上旬から中旬
- 本試験:1月中旬から下旬の2日間
高校生は学校で一括して出願などを行いますが、高卒生は自分で出願しなければいけませんので、日程などをしっかり把握しておきましょう。
共通テストは、全教科、科目すべてマークシート方式での実施です。基礎的な学力が身についているかをはかるため、各大学で行われる試験と比べて難しい問題が出題されることはありません。
共通テストを利用するメリットとデメリット

私立大学を志望する場合、「共通テストよりも志望校対策に時間を割いた方がよいのではないか」と共通テストを利用するべきかどうか迷っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、共通テストを利用するメリットとデメリットについてご紹介します。
共通テストを利用するメリット
共通テストを利用するもっとも大きなメリットは、複数の大学の対策を同時に行えることです。共通テストの点数さえ取ることができれば、複数の大学に出願して合格を勝ち取れる可能性が高くなります。
また、共通テストは一般選抜と比べて受験料が安いため、利用すると受験費用が抑えられます。しかも、地元で受験できるので、地方から都内などにわざわざ遠征費用をかけて出てくる必要もありません。そのため、お金と時間を効率的に使えるということになります。
これまでのセンター試験利用入試は、「受かればラッキー」「一般で落ちたときの滑り止めに」という感覚で受けることが多数でした。
しかし、これからは大学側の「共通テスト利用入試を重視していこう」という動きも多くみられているため、確実に共通テストの重要度は上がっています。
共通テストを上手に利用すれば、大学ごとに個別の対策をしなくてもよくなるケースもありますので、積極的に利用すべきなのです。
共通テストを利用するデメリット
私立大学受験で共通テストを利用する場合、難関私立になるほど学力の高い方達が出願します。しかも、募集人数自体が少ないため倍率が高くなり、合格ラインが上がってしまう可能性があります。
また、共通テスト利用入試は受験科目数が多くなる場合があります。とくに国公立大学の多くは5〜6科目を指定されることが多いです。
その一方で、私立大学の一般選抜では3科目受験が基本となっているため、苦手科目がある方や準備期間が少ない方は一般選抜の方が有利になることがあります。
加えて出願時期にも注意が必要です。共通テスト利用入試の出願期間は大学によって異なります。
中には共通テスト実施前に出願しなければいけない場合もあるため、志望校の決定をできるだけ急ぐ必要があるのです。
多くの大学を共通テスト利用で受験する場合は、それぞれの大学ごとの出願スケジュールを把握しておくようにしましょう。
2021年度の共通テストを受けた現役生の感想

2021年1月16日17日に実施されたはじめての「大学入学共通テスト」の第1日程。共通テスト一期生として実際に受験をした現役生は、率直にどんな感想をもったのでしょうか。
以下は、試験全体についての感想です。
問題の情報量と文章量が増えた。限られた時間でいかに早く正確に問題を読み取れるかが鍵だと思います。
文章はもちろん、表や資料から必要な情報を判断し抜き出して回答するタイプの問題が多かったです。文章量が多く、問題のページ数が大幅に増えた科目もありました。
とにかく問題数が多かったです。時間配分が難しく、全部解くことができませんでした。もう少し試行調査に似た感じの問題だったら嬉しかったです。
全体的に過去問と比較して難しくなったと感じました。自分の知識をどれだけ応用できるか、柔軟に考えることができるかが問われていると思います。
はじめて行われた共通テストでは、情報量と文章量が増えたことで時間配分が上手にできなかった方が多くいたようです。共通テストで力を発揮するには、これまで以上に読解力や情報処理能力が重要になってくるでしょう。
たしかに暗記や知識だけでは解けない問題も増えたといえますが、だからこそ基礎をしっかりと固めることが大切だと感じた方も。
全体的な難易度としては従来のセンター試験とさほど変わらない印象を受けた方もたくさんいましたが、英語についてはリーディングとライティングともに出題形式に戸惑った方が非常に多くいました。
これから共通テストを受験する予定のある方は、まずは基礎をしっかりと勉強し、過去のセンター試験の問題をたくさん解いておくとよいでしょう。
まとめ
大学共通テストの詳細と、利用するメリットとデメリットについてご紹介しました。
共通テストは、主に国公立大学を志望する方や私立大学の共通テスト利用入試を活用する方が受験する試験です。
教科や科目数、実施日程などがセンター試験と変わらないため、一見違いがわからないかもしれませんが、共通テストはセンター試験よりも思考力や判断力をはかる問題が増えます。
とはいえ、従来のセンター試験の問題が基礎になっているため、問題の傾向などについては知っておく必要があります。高校で学習したことをしっかりと理解しておくことが求められますので、センター試験の過去問などを利用して対策を行っておきましょう。
センター試験の受験をお考えの方はぜひ本記事を参考にしてみてくださいね。