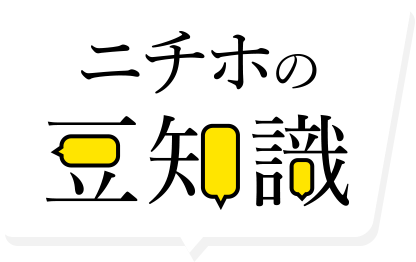大学入試制度の基礎知識!新入試制度や大学入学共通テストについて解説
- 入試情報
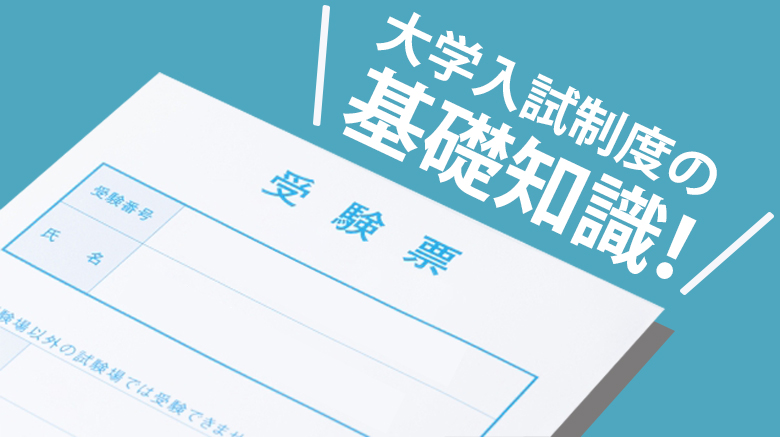
大学入試は多様化しているため、受験について考えたときに複雑さを感じてしまうこともあるのではないでしょうか。
2021年度入試からは、いよいよ新しい入試制度に変わりました。受験方法や全体的な流れは大きく変わることはありませんが、いくつかの変更点があります。
中でも大きな変更点は大学入試センター試験が「大学入学共通テスト」に変わったことです。
この記事では、新しい大学入試制度の変更点や大学入学共通テストとはどのようなものなのかについて詳しく解説していきます。
大学受験の前には、最低限必要な知識を身につけておくことも大切です。ぜひ記事を参考にして新大学入試制度について知り、受験勉強に取り組んでみてください。
目次
新大学入試制度で何が変わった?

新大学入試制度でもっとも大きく変わったのが大学入試制度センター試験から「大学入学共通テスト」となったことです。
これからの大学入試制度は、従来のような知識の量を確認するための試験ではなく、身につけた知識を使って自分から問題を見つけ、それに対する答えや新しい価値を生み出す試験となります。
思考力や表現力、判断力が大きく問われることになる大学入学共通テストでは今までとは出題傾向や形式も変わってくるため、受験生はそれに合わせた対策を行うことが大切です。
また、国公立大学の二次試験や私立大学が独自に行う入試で、高校で取り組んできた活動が評価の対象となるというのも変更点の一つです。
新大学入試制度の基礎知識

新しい大学入試制度では、入試区分の名称も下記のように変更となりました。
- 一般入試⇒一般選抜
- AO入試⇒総合型選抜
- 推薦入試⇒学校推薦型選抜
名称だけではなく、評価のポイントも変わりました。一般入試は学力重視、AO入試は学力以外を重視、推薦入試は学校の推薦というのが大きな特徴でしたが、新しい大学入試制度では「学力の3要素」をすべての入試で評価します。
新しい大学入試制度を理解し、対策を行うためにはこの「学力の3要素」についてしっかりと理解しておく必要があります。これらは元々、小学校教育で規定されたものですが、大学入試改革を推進するうえでの基本的な考えとしても採用されています。
| 知識・技能 | 持っている知識と学んだ内容を関連付けて理解を深め、さまざまなシーンで活用する能力 (筆記試験・口頭試問・実技を含む課題などで確認) |
|---|---|
| 主体性・多様性・協調性 | 自分を客観的に見て周囲との価値観の違いを理解し多様性を受け入れ協力し合い、それによって育んだリーダーシップや思いやりをどのように学びに活かすか、社会とかかわっていくかを考える能力 (記述課題・面談・面接などで確認) |
| 思考力・表現力・判断力 | 目の前にある問題に対し、自分で答えを見つけるための力で、考える中で自分にはどのような部分が足りないかを理解し、不足していると考えられる部分を勉強することにより、よりこれらの能力が深まります。(記述課題・小論文などで確認) |
学力の3要素は上記のように多様な方法によって確認されます。
各大学の個別選抜でも、調査書を点数化して、面接を行うなどが見られます。
一般選抜(旧一般入試)
国公立大学を目指している方がまず考えるべき大学入試が一般選抜(旧一般入試)です。
近年では総合型選抜や学校推薦型選抜など特別入試の募集枠が広がっていますが、それでも国公立大学の募集人員の割合のおよそ8割が一般選抜となっています。
一般的には、1月中旬に実施される大学入学共通テストの特典と、2月下旬から実施される大学別の個別学力検査の合計得点で合否が判定されます。
原則として大学入学共通テストを受験する必要があり、自己採点後で志望大学に願書提出を行います。
分離・分割方式
個別学力検査は分離・分割方式と呼ばれる方式で行われます。これは、募集人員を前期日程と後期日程に振り分けて選別するというもので、それぞれ1校ずつ出願が可能です。
別の大学や学部を受験することもできますし、同じ大学の同じ学部を2回受験することもできます。(中期日程を設定している大学の場合は最大で3校受験可能)
分離・分割方式で注意しなければならないのが、第1志望校は前期日程で受験する必要があるということです。前期日程で合格し入学手続きを行うと中期日程や後期日程で受験していたとしても合格の権利を失うため、受験機会は複数あるものの、前期日程が中心となった仕組みです。
2段階選抜
2段階選抜とは、大学入学共通テストの成績によって個別学力検査(2次試験)を受けられるかどうか、選抜を行う制度のことです。
2段階選抜を行うかどうかは大学によっても異なり、志願者数が多く集まった場合に2段階選抜を行うという大学が多く、医学科や難関大学など志願者が集まるケースで実施されています。
これはつまり、大学入学共通テストの成績次第では個別学力検査を受けられないまま不合格となってしまうこともあるということです。そのため、大学入学共通テストでしっかりと結果を出すことが大切です。
総合型選抜(旧AO入試)
総合型選抜では受験生が提出するエントリーシートなどのほか、論文、面接、プレゼンテーションによって意欲や適性、能力を総合的に評価します。
2021年度入試からは学力を確認するための大学入学共通テストなどの評価方法の活用も必須となりました。
一般的な選考方法が1次に書類審査、2次に面接や小論文というものですが、このほかにもスクリーニングなどに出席し、レポートを提出させるという選考方法などがあります。
ほかの入試方法に比べて、総合型選抜では学校側は受験生の能力や適性、意欲、学力など、じっくり時間をかけて総合的に評価します。受験生が行わなければいけない事前準備も多いため、総合型選抜を選ぶ場合は早いうちからしっかりと対策しておかなければなりません。
総合型選抜は主に下記のようなタイプがあります。
| 選抜型 | 小論文、レポート、長文の自己推薦書や志望理由書などが課され、受験生は早めの対策が必要。国公立大学、難関大学に多い |
|---|---|
| 対話型 | 面談や面接を複数回行い、学ぶ意欲や受験生の人物を評価する。私立大学に多い |
| 体験・実技型 | 実験、模擬試験、セミナーなどが含まれた入試プログラムに参加することが出願条件。課題提出などが求められる |
私立大学の総合型選抜には事前面談、予備面談など対話型が多く、その大学で学びたいという意欲や選択した大学や学部への適性がより重視されます。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)
学校推薦型選抜は国公立大学の90%以上が行っており、一般選抜に次いで多い方式です。
多くの大学が専願制ですが、最近では併願制も増加してきています。
私立大学では学校推薦型選抜の入学者比率は50%近くを占めていますが、国公立大学の場合は私立大学と比べると募集人数が少なくなっており、厳しい成績基準が設けられている場合もあります。
出願のためには出身高校長の推薦を受ける必要があり、誰でも出願できるわけではありません。中には「○浪まで」や、学習成績の状況などの条件が付いている場合もあります。学校推薦型選抜は大きく分けて下記の2タイプがあります。
| 公募制 | 出身高校長の推薦があり、大学の出願条件をクリアすれば受験可能 |
|---|---|
| 指定校制 | 大学が指定した高校の生徒を対象としており、国公立大学ではほぼ行われておらず、私立大学が中心 |
大学入学共通テストとは?

今まで30年にわたって行われていた大学入試センター試験が2021年度から「大学入学共通テスト」に変わりました。これが新しい大学入試制度の中でもっとも変化した部分です。
実施日程や出題教科・科目数は大学入試センター試験と変わりませんが、基礎的な内容だけでなく思考力や判断力、表現力が問われる問題まで、幅広い問題が出題されるようになっています。
大学入学共通テストに変わった理由は?
大学入試センター試験も高校の先生の間で評価が高かった試験ですが、なぜ大学入学共通テストに変わったのでしょうか?
その理由が、国が推進する高大接続改革の一つである大学入試改革です。
グローバル化、少子高齢化、情報社会の進展など急速に変化し先を予想できない現代社会では自ら問題を見つけ出す力や、新しい価値を創造する力が重要だとして、それらの力を育むことにつながる大学入学共通テストに変わりました。
共通テストとセンター試験の違い
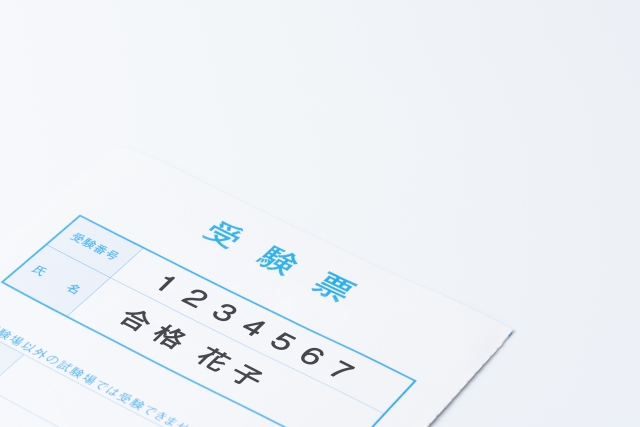
大学入学共通テストの問題は大学入試センター試験の内容を踏襲した内容となっていますが、異なる特徴として下記の点が示されています。
- 思考力・活用力が問われる問題が重視される
- 地域の課題など身近な題材や、実用的な文章を題材とした問題が出題される
- 1のような問題ではこれまでになかった形式の解答方法が取り入れられる
また、大学入学共通テストでは、英語の出題内容や配点に変更があります。
- 大学入試センター試験…筆記200点、リスニング50点
- 大学入学共通テスト…リーディング100点、リスニング100点
リーディングは英文を読むのが中心となりますが、読む時間が増えても試験時間は同じです。時間配分をしっかり考えておかないと、時間が足りなくなってしまう可能性もあるため注意しましょう。
出題科目・配点・試験時間・解答方式
大学入学共通テストは下記の6教科30科目で構成され、英語では配点の変更、数学Iと数学I・Aでは試験時間が60分から70分に変更となっています。
| 教科 | 科目 | 配点 | 試験時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 国語 |
|
200点 | 80分 | |
| 地理・歴史 |
|
1科目100点
2科目200点 |
1科目選択:60分
2科目選択:130分(解答時間120分) |
|
| 公民 |
|
|||
| 数学 | ① |
|
100点 | 70分 |
| ② |
|
100点 | 60分 | |
| 理科 | ① |
|
2科目100点 | 2科目選択:60分 |
| ② |
|
1科目100点 | 1科目選択:60分
2科目選択:130分(解答時間120分) |
|
| 外国語 |
|
リーディング:80分
リスニング:30分 |
各100点で合計200点 | |
|
80分 | 200点 | ||
まとめ
大学入試制度は複雑な部分もあるため、それぞれの大学入試の内容をしっかりと理解し、自分が希望する大学入試に合った対策を行う必要があります。
新しく始まった大学入学共通テストは思考力・判断力・表現力が求められる問題が増加しますが、基本は大学入試センター試験の問題です。問題傾向や選択肢ついても把握しておくようにしましょう。